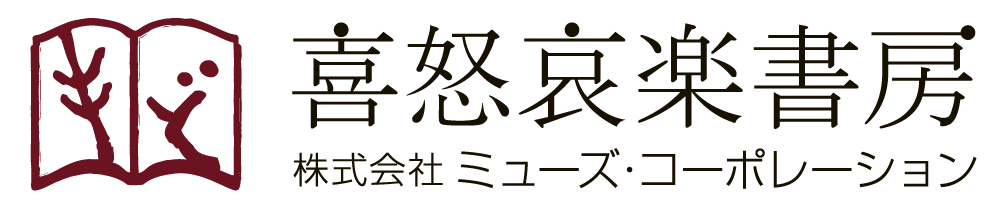今年2月『越後荒川保内・羽ヶ榎村 齋藤庄左衛門家の謎の研究 ― 祖先へのレクイエム(鎮魂の譜)として ―』をまとめられた齋藤榮様にお話をお聞きしました。
Q なぜこの本をまとめようと?
父の祖父である、齋藤庄左衛門の伝説的な話は耳にしていた。12歳年上の兄からは、火災に遭う前の家には「鎧や兜、槍がずらりと並んでいた」とか、興味をそそる話を聞かされていた。新年の挨拶に叔父が来てお酒をつけると、もう先祖の話。いろりを囲んで私も黙って聞いていた。いったい祖先はどうであったのか。伝承が語るほどの家ではないという叔父もいれば、由緒ある家柄だと信じて疑わない叔父もいた。その後者の叔父に「庄左衛門の謎を解明できるのはお前さんしかいない」と頼まれたが、教員になって間もない頃でそれどころではなく、以後何十年も忘れていた。
Q それがどうしてこの度?
平成29年のある日、所用があってかつて北越後を代表する豪農であった国井家に立ち寄った。用事が終わって庄左衛門のことを聞こうと、国井家の伝承の有無を尋ねたところ、即座に「ありますよ。家譜に書いてある」と、コピーをくれた。それを読んだ瞬間、先祖は思ったより上のレベルだということが想像された。姫路の藩主本多忠孝(徳川家康の四天王の一人本多忠勝の子孫)が、村上十五万石の藩主に国替えを命ぜられ初めて村上城に入る前日、入城準備のために羽ヶ榎村の齋藤庄左衛門家に一泊したことが記されていたのだ。その時、先の叔父の言葉を思い出した。この資料から、何とか先祖の実態がつかめるのではないかと、勇気と確信を得た。それが2年前の78歳のとき。多くの文献に当たるには視力や根気が弱ってきている、よし80歳までの2年間でやり切ろうと決意した。
Q 順調に進みましたか?
ところがいざ研究を始めるとどこから手をつけたらいいのか。ただ無手勝流にやっていても仕方ないと、手始めに荒川町郷土史を読み、来る日も来る日も図書館に通った。ある日、全国版の豪農渡辺家の借金の証文が出てきた時は大いに喜んだ。でも意味が分からず、その虎の子の借用書を持って紹介してもらった専門家のところに行った。開口一番「ご先祖は侍ですね。給金をもらっていますよ」と。その村上市の郷土史家には様々にアドバイスをいただき、最終的には庄左衛門の祖先は本庄繁長の近習だったことが判明した。祖先が生き生きとよみがえる姿、それを見るというか読むのだから、それは楽しいものだった。最初は絶望していたが、人から人へとつながって次第に探求心が満たされていった。ただ、それをわかるように書く、まとめることは大変でしたね。

Q 完成した本は?
短期間でよく調べたとか、表題が長すぎるとかいろいろ言われる(笑)。喜怒哀楽書房さんとは長いお付き合いで、私のことをよくわかっているから無理を言えた。また、先祖を学ぶことで改めて日本史を学んだ。宗家がつぶれたことと幕藩体制がつぶれたこと、時代の大きな波の中でみんな絡んでいる。ちょっと急ぎすぎたかもしれないが、これであの世に行って祖先に顔向けができる。
Q 諦めずによくまとめられました
調べ始めてから1年10カ月で本が完成。昔から意地っ張りな性格なんです。15歳で進路を決める際も、両親の反対を押し切って中学を出て東京で就職をした。明確な目標を持ち、働きながら夜間の定時制高校で学ぶ友だちがかっこよく見えたんですね。塗装会社や印刷会社で働きながら自力で高校を出た。回り道をしたとも思うが、今日あるのはその時があったから。共同生活をしていた先で、大卒の知人が授業の話をしてくれ、その影響で学問が楽しくなった。この先の人生、ずっと学問に触れて生きたいと思うようになり、大学を出て教員になって新潟に戻ってきた。新発田高校に赴任し、27歳のとき剣道部の顧問に。自分もできないと真の対話が成立しないと、部員から手ほどきを受けた。
Q 剣道は七段の腕前とか
今でも毎日竹刀を振っている。剣道は心気力だが、この歳になると心と気しかない。心気はなんで養われるか? それは覚悟。生きる覚悟、死ぬ覚悟、そしてこれを書く覚悟(笑)。目を覚ますとあとわずかじゃないかという想念がわく。中村元訳の『ブッダ最後の旅』が愛読の一書。残っている命を大事にするということは、自分のやるべきことをやって死ぬ、そういう教えだと思っている。お釈迦様はアーナンダに「もうこのへんでいいだろ、俺の寿命はもう尽きている」と言って入滅する。そんな生きざま、心境でありたい。次は、パスカルの研究を始めています(笑)。
★剣道の話になると、さっと立ち上がり「この間、距離感が大事なんです」と、今朝は何を課題にどういう人を想定して竹刀を振っていたかをジェスチャー付きで解説してくださる。「どこに立つのが一番理想的か、考えて打つようではだめ、考えないでできるようにならないと」と。目指すところは「剣道という道の奥」とも。何においても、打ち勝つのは他者ではなく、己である。(木戸敦子)