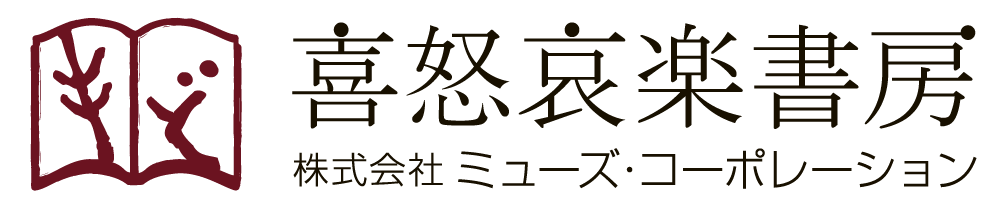昨年11月に句集『柘榴』を出版された祐森様に、お話をお聞きしました。
Q 素敵なお着物ですね
着物を着る習慣が身についたのはお茶のおかげ。
大学入学と同時に「お茶をしなさい」と母に言われ、母の顔を立てて1年だけという約束が現在まで35年も。正座に慣れるのに2年近くかかった(笑)。
見た事も触った事もないものばかりで、和室での立ち居振る舞いからお道具まで、やることなすこと知らない世界。隅から隅まで日本の伝統文化一色で引き込まれた。
お薄茶で使う茶杓の銘は季語そのものだし、お茶の先生が俳句をされていて、俳句の嗜みも必要と思い興味を持った。それが35歳の頃。
Q その後は?
いくつかの結社の雑誌を取り寄せ、同じ川越にある「遠嶺」に手紙を書くと「初心者講座にいらっしゃい」と。
ところが行った日は最終回で、いきなり俳句を三句用意するとのこと。
とまどいながら初めて出したのが「シャボン玉天球の青分かれゆく」という句で、想い出深く今回の句集の最初に入れた。
驚いたことにその句が最高点句になり、そのまま「遠嶺」に入って9年間、様々なことを経験させていただいた。
Q 俳句の素養があったのですね
どうなのでしょう。一人っ子で鍵っ子だったから、よく家で詩とか書いていた。
結婚してからは小説を文芸誌に応募し、いいところまでいった作品のタイトルが『柘榴』だった。それも一番最初に書いたもので以後は選ばれなかったから、小説は無理かなと。
次第に子育てで忙しくなり、そんな時にお茶の先生が「俳句はどう?」と勧めてくださり「小説に比べたら簡単にできるだろう」と思ったらできない(笑)。
短いってすごく難しいなぁ、でも面白い!ということで方向転換を。
Q 今回の『柘榴』が第一句集?
「遠嶺」を退会後、水内慶太先生に出会い「月の匣」の創刊とともに編集長に。とても自分の句集まで手が回らなかった。
今回句集を編んだことで、日々休みなく俳句を詠んでいる時には見えなかったものが、段階を踏んでわかってきた。
選句をしている時、一冊の本になった時、読んで感想をいただいた時、今後どういう俳句を作り、どう変わっていきたいのか。
客観的に自分の俳句を見られたし、句集がなければ昨日と同じことを続けていただろうから、遅ればせながらまとめてよかった。
そして、句集を出したことで生まれ変わりたいと思った。

Q どのように?
変わりたいと思っている割に、根っこは変わらないから、今後どう表現するかということ。ただ変えるには荒っぽいことをしないと変わらない。
祖父は俳句の結社を持っていた人で、今、手元にあるこの薄っぺらい句集だけが残っている。
五七五に縛られていないし、今までの私の作り方だったらこれはダメでしょという句ばかり。
それなのに不思議と魅力を感じ、このリズムを身につけられたらいいなと繰り返し読んでいる。
とても刺激になるし、冒険するきっかけになればいいと思って。最初は受け入れられなかったが、今読むと共感するし、やはり同じ血が流れていると感じる。
Q これからは
初め俳句は自分を晒しているみたいですごく恥ずかしかったが、いつの間にか見られることを前提に作っているという面白い文芸。
この面白さがわかれば俳句を続けてもらえるだろうと思って、カルチャー教室でもアピールしている。
皆さん人生経験が豊富で優しくて「先生は若いから知らないよね」とフォローしてくださる。でも知らないと鑑賞ができないから、去年は奈良に4回行き一人旅に開眼した(笑)。
長年やっていると、どうしても自己類想を作ってしまいがち。それだけは避けたいから、常に今をはみ出していきたい。
句集『柘榴』より
遠景の少女へと吹くしやぼん玉
紅波甲や恋の遍歴きかれをり
小ぎれいに暮らし小菊を輝かす
黒髪につながってゐる冬の海
★一度、句会を取材した際に祐森さんの席題の句のすばらしさに目をむいた。今は月に10の句会に参加し、3カ所のカルチャー教室で教えているが、かつては1日5句作ることを3年続けたり、編集長だったころは本を多読し文法もかなり勉強したとか。一朝一夕には成し得ない鍛錬が集約して今がある。ただそんなことは一切感じさせず、何においてもスマートでおしゃれで、ワインを飲みながら語る様はほれぼれする。常にここではないどこかへ―。とどまることなく、新しい俳句を作りたいとの言葉が印象的だった。(木戸敦子)