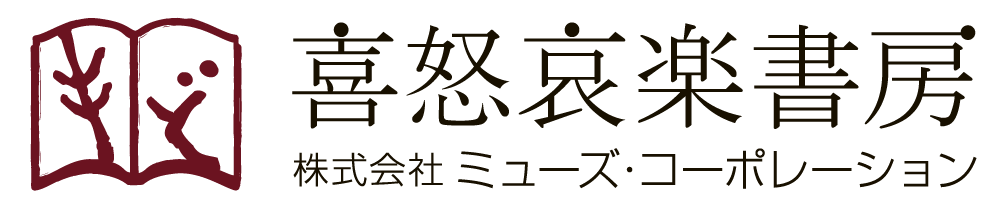喜寿を迎える五月、第二句集『中川肇句集』を上梓した中川肇さん。ご自身の〝或るギャラリー〟で、お話をうかがいました。
■第二句集出版のきっかけとテーマは?
第一句集出版から7年経ち、そろそろ、と思った。今回は形から入りました。第一句集のとき作った函(本のケース)が600個近く余っていたから、それを使おうと。本文用紙を決め、総ページを決め、句数を決め…と外側から作っていくことにして、木戸さんをびっくりさせた。出来上がったときはほっとしたね。いい函だったから、活かせて嬉しい。「第一句集に似てますね!」と言われたけど、同じもの(笑)。
収録した句は、句会に出す実験句とはちがって、自分が残したい句。句集は自分史と同じ。だからちょっと変かもわからないけど、あとがきを入れないで、詞書をいっぱいつけて、略歴を巻末につけた。
テーマはもともと何もなく(強いて言えば最初から生と死)、母が長寿で他界したから、それは当然中心になった。第一句集は父に捧げるものだったし、次に作るとしたら女房かな。
■第一句集のタイトルは『中川肇一行詩集』。発行されている詩誌「宙」では俳句と詩が一緒に掲載されています。
「詩と俳句の二刀流ですか」ときかれることもあるけど、詩も俳句も同じ「詩」だと思っている。高校の頃はとにかく「表現」に憧れて、ジャンルにとらわれず短歌や詩や俳句をいろんなところに投稿した。そこでいちばん引っかかったのが詩。退職して俳句を本格的に始めるようになり、俳句も詩だ、詩でなければと強く思った。それで詩人にも俳句を書かせたいと「短詩の試み」という同人誌になり(今は個人誌)、「宙」という名前で発行している。
■本当に本がお好きなのだと感じます。
物心ついたときから、本をつくる仕事に就こうと思っていた。忘れられないのは、六年生のときに買った佐藤紅緑の『一直線』。もらった小遣いを減らさないよう、本屋さんへの八キロの道のりをバスを使わずに歩いて行った。それが、帰りに縁日を見てたら、小脇に抱えてた本がなくなってたの。血眼になって探したけど、なかった。あれは強烈な思い出。
■一言でいうと、本はどういう存在ですか。
生涯の恋人。一病息災の「一病」みたいなもの。内容より、本そのものが好き。本に埋まって死ぬだろうね。
■ギャラリーをはじめたきっかけと、「或る」に込められた意味を教えていただけますか。
「或る」はもともと「ある」。22歳のとき詩誌「時間」の同人4人で「ある」という同人誌を始めた。「ある」とは「在る」存在(この意識がいちばん強かった)、そして「アール」(芸術)、そして「或る」。よくばって三つの意味を込めた。同人誌は3年ほどで終わったが、その後、まど・みちお先生と知り合い、先生にも書いていただき始めたのが「或る」。「或る一つの」というつつましい感じを込めた。そして会社を卒業と同時に始めたギャラリーの名にした。
■書き続けたり、表現したりする「原動力」は?
生きた証を残したいという、やむにやまれぬもの。それがたまたま、わずかな才能にすがって、書くという行為になっている。父は必然的に絵だったが、ぼくはたまたま言葉。だから本が好きなんだろうね。あとは、人が好きなんだね。人たらしなんだと思う。
■これからは?
次は野菜の花の本の出版を考えている。大好きな野菜、その花が意外に美しいことに気づき、撮りためるようになったことがきっかけ。次回も元気で出版したいなあ。
春の水おぼれていいと思ひけり
母がなほ小遣くれる木の葉髪
椎拾ふつくづくおれは老童子
につぽんのやさしき山の寝釈迦かな
生涯をうべなふごとし大夕焼
(『中川肇句集』より抜粋)
★「何回出しても句集名は中川肇句集。それでいいと思うんだよね。父に捧げたり、母に捧げたりというのはあるけど、根っこにあるのは、自分」。ギャラリーをもち、詩誌を発行し、写真を撮り――と自身の「表現」に休みがない。周りに「大人気ない」といわれるほど率直、それなのに不思議と悪感情を抱かせない。常に受け容れる度量と愛情があるからなのだろう。人と語り、呑むことを心から楽しむ中川さんの周りには、人が集まってくる。「花の嫌いな人っている?いないでしょう。みんな好きなんですよ結局。人間も花なんです」と話す中川さんの原稿は、いつも分かりやすく、何よりその文字がやさしい。
(菅真理子)